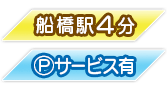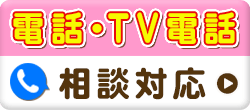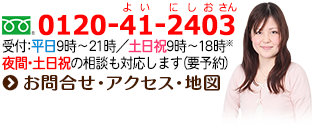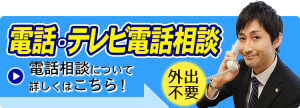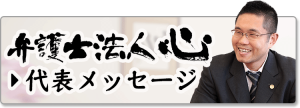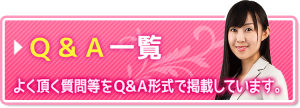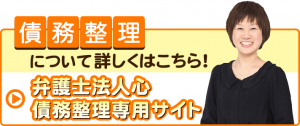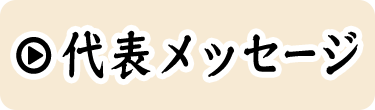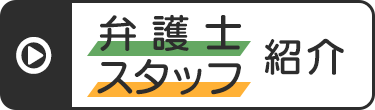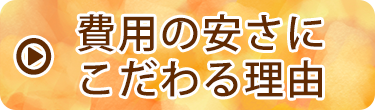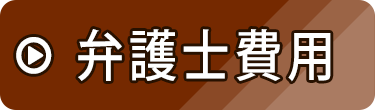借金の時効が成立するまでには何年かかるか
1 借金の消滅時効が完成するまでの期間の概要
民法改正の施行日である令和2年4月1日以降に発生した借金を返済する債務については、弁済期から5年を経過すると消滅時効が完成します。
令和2年4月1日以前に発生した債務のうち、個人や会社組織でない信用金庫等からの借金に基づくものについては、弁済期から10年を経過すると消滅時効が完成します(借り手が商人でない場合)。
また、確定判決また確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利は、権利の確定から10年で消滅時効が完成します。
以下、詳しく説明します。
2 借金の消滅時効が完成するまでの期間
令和2年4月1日以降に発生した一般債権(その原因となる法律行為も令和2年4月1日以降である)の消滅時効ついては、民法166条第1項に次のように定められています。
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
上述の一または二のいずれか早い方で、消滅時効は完成することになります。
借り入れ先が貸金業者等である場合には、通常であれば弁済期を過ぎた時点で権利を行使することができることを知りますので、5年間で消滅時効が完成します。
令和2年4月1日以前に発生した債務のうち、個人や会社組織でない信用金庫等からの借金に基づくものについては、弁済期から10年経過しないと消滅時効が完成しません。
例えば、債務整理の場面でよくみるものとしては、日本学生支援機構からの借入金(奨学金)が挙げられます。
3 確定判決また確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利
判決で確定した権利の消滅時効については、民法において、別途次のように定められています。
第百六十九条 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。
2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。
実務上、債務整理の場面で問題となるのは、債務者の方において判決が確定していたことの認識がないケースです。
精神的に追い詰められていたり、頻繁に住所を変えざるを得なかった等のご事情により、訴訟が提起されたこと自体を認識していなかったり、判決が下った記憶が曖昧であったりするということがあるためです。
消滅時効を援用するため、貸金業者等から取引履歴の取得をした際、確定判決が存在し、消滅時効が完成していないことが判明することがあります。
このような場合、任意整理など、他の債務整理手法を用いることを検討します。